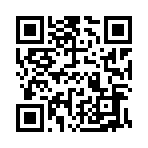2008年06月26日
生命のコントローラー(8)~ビタミン・ミネラル(微量栄養素)
ビタミン・ミネラルの協力者
ビタミン・ミネラルの働きを補助する栄養素
脂溶性ビタミンのビタミンA、D、Eなどは、
食物中の油に溶けると吸収しやすくなります。
したがって、油の少ない食事では脂溶性ビタミンの吸収が悪くなります。
ビタミンやミネラルが腸の粘膜を通過するときや運び出すときに、
タンパク質の協力が必要になってきます。
また、タンパク質は、ビタミンやミネラルと結合して、
血液の中を移動していきます。
つまり、タンパク質が少ない食物では、
ビタミンやミネラルの吸収に影響がでてきます。
ミネラルの多くは、
酵素(化学反応を促進させるためのタンパク質)の構成成分となって、
機能を果たしています。
したがって、酵素となるタンパク質がしっかりと合成されなければ、
ミネラルの機能が半減してしまいます。
ビタミンやミネラルが効率よく働くには、
補助してあげる他の栄養素が必要です。
ビタミン・ミネラルだけでは効果が半減・・・事例
飢餓地域の人たちは、ビタミンAの欠乏により、
失明してしまう問題があります。
この人たちにビタミンAを投与するだけでは、
失明の予防にならないことがわかっています。
ビタミンAの投与と同時に、
その他の栄養状態を改善しなければ、
失明の予防にならないのです。
つまり、ビタミンやミネラルが効率よく働くには、
補助してあげる他の栄養素が必要です。
最後に、バランスの良い食事が大切です
ビタミン・ミネラルは、
私達人間のからだを調節するという、とても重要な働きをしています。
その重要性から、
論文や文献によっては三大栄養素の炭水化物、脂質、タンパク質と
ビタミン・ミネラルをあわせて「五大栄養素」と位置づけているものもあるほどです。
さらに、最近の研究から「薬理効果」を見出され、
ビタミン・ミネラルの果たす役割は、
まさに私達人間の「生命のコントローラー」なのです。
しかし、健康を維持するためには、
特定のビタミン・ミネラルだけを摂取すればよいものではありません。
私達人間のからだはとても複雑に出来ていて、
ビタミン・ミネラルは相互に関係しながら、
他の栄養素に助けられて、はじめて効率よく効果を発揮します。
したがって、
私達の健康を維持するためには、
いろいろな食物をバランスよく食べることが重要です。
健康工房 紀の郷
http://www.health-navi.net/
Posted by 健康工房 紀の郷 at
14:07
2008年06月23日
生命のコントローラー(7)~ビタミン・ミネラル(微量栄養素)
ビタミン・ミネラルによる予防と回復
薬の機能
ビタミンやミネラルは栄養素としての役割があります。
ところが、最近の研究では、
栄養素のほかに新しい機能を期待するようになってきました。
それは、病気に対して薬として働いたり、
病気への予防の効果が出る「薬理効果」という機能です。
例えば、
骨粗鬆症の予防は、ビタミン・ミネラルが大きく関与していることは周知のことです。
さらに、食事などが深くかかわっているガン、心疾患、脳疾患などの成人病の予防に、
効果があることがわかってきました。
このように「薬理効果」が見出されたことによって、
ビタミン・ミネラルは広く関心がもたれています。
免疫力を上げる
人間には、自然に治癒する能力があり、
自律神経系、ホルモン系、免疫系の三つのバランスが大切とされています。
その中の免疫とは、私達人間のからだが、
侵入してきた病原菌などや変異したガン細胞などを除去することです。
この免疫力を向上させるものとして、
ビタミンA、C、Eがあります。
※病気の予防と回復のための栄養素
ガン
ビタミンA、B群、C、E、セレン
心臓病
ビタミンB群、C、E、カリウム、カルシウム
骨粗鬆症
カルシウム、マグネシウム、ビタミンC、D
糖尿病
ビタミンB群、C、E、ナイアシン、クロム、マンガン
更年期障害
ビタミンB群、C、E、鉄、セレン
脳卒中
ビタミンB群、C、E、亜鉛、マグネシウム、マンガン
アレルギー・ぜん息
ビタミンA、B群、C、E、マンガン
リュウマチ
ビタミンB群、C、E、カリウム、カルシウム
胃潰瘍・十二指腸潰瘍
ビタミンA、B群、E
貧血
ビタミンB群、C、E、葉酸、鉄、銅、マンガン、マグネシウム
神経痛
ビタミンB群、C、E、ナイアシン、パントテン酸、マグネシウム
健康工房 紀の郷
http://www.health-navi.net/
Posted by 健康工房 紀の郷 at
10:31
2008年06月22日
生命のコントローラー(6)~ビタミン・ミネラル(微量栄養素)
ビタミン・ミネラルは組み合わせ
ビタミン・ミネラルは組み合わせです。
ビタミン・ミネラルは組み合わせによって色々な働きをします。
ビタミン・ミネラルの相互作用
ビタミンやミネラルは、そらぞれ単独で働くのではありません。
いくつかが同時に共同して働き、効果を発揮しています。
ビタミンとミネラルが様々に組み合わさり、相互に働き合って、
人間のからだを正常に維持しています。
例えば、健康な骨をつくるために必要なのは、カルシウムだけではありません。
カルシウムが効率よく吸収・沈着されて働きやすくなるためには、
ビタミンD・ビタミンC・マグネシウムが必要なのです。
ビタミンDがカルシウムを運び沈着させます。
ビタミンCがカリウムの働きを高めます。
そして、マグネシウムがカルシウムの働きを助けることによって、
健康な骨や歯をつくります。
このように、ビタミン・ミネラルはお互いに関係しあって、
共同で最高の効果を発揮するようにできています。
※ビタミン・ミネラルの組み合わせによる働き
エネルギーをつくる
ビタミンB群、鉄、マグネシウム
健康な血液・血管を作り、血圧を正常にする
ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンE、葉酸、
鉄、銅、マンガン、コバルト、ナトリウム、カリウムなど
精神を安定させる
ビタミンB群、マグネシウム、鉄、銅、カルシウム、亜鉛など
健康な皮膚、粘膜をつくる
ビタミンA、ビタミンB群、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、リン、カルシウム、亜鉛など
健康工房 紀の郷
http://www.health-navi.net/
ビタミン・ミネラルは組み合わせです。
ビタミン・ミネラルは組み合わせによって色々な働きをします。
ビタミン・ミネラルの相互作用
ビタミンやミネラルは、そらぞれ単独で働くのではありません。
いくつかが同時に共同して働き、効果を発揮しています。
ビタミンとミネラルが様々に組み合わさり、相互に働き合って、
人間のからだを正常に維持しています。
例えば、健康な骨をつくるために必要なのは、カルシウムだけではありません。
カルシウムが効率よく吸収・沈着されて働きやすくなるためには、
ビタミンD・ビタミンC・マグネシウムが必要なのです。
ビタミンDがカルシウムを運び沈着させます。
ビタミンCがカリウムの働きを高めます。
そして、マグネシウムがカルシウムの働きを助けることによって、
健康な骨や歯をつくります。
このように、ビタミン・ミネラルはお互いに関係しあって、
共同で最高の効果を発揮するようにできています。
※ビタミン・ミネラルの組み合わせによる働き
エネルギーをつくる
ビタミンB群、鉄、マグネシウム
健康な血液・血管を作り、血圧を正常にする
ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンE、葉酸、
鉄、銅、マンガン、コバルト、ナトリウム、カリウムなど
精神を安定させる
ビタミンB群、マグネシウム、鉄、銅、カルシウム、亜鉛など
健康な皮膚、粘膜をつくる
ビタミンA、ビタミンB群、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、リン、カルシウム、亜鉛など
健康工房 紀の郷
http://www.health-navi.net/
Posted by 健康工房 紀の郷 at
09:01
2008年06月19日
生命のコントローラー(5)~ビタミン・ミネラル(微量栄養素)
ミネラルの働き
ミネラルもビタミンと同じように酵素の働きを補い、
体液、骨の合成、神経組織をつくるためにも必要なものです。
ミネラルは、
精神とからだを正常に働かせるために欠かすことの出来ないものであり、
体液の微妙なバランスを保つためにも働いています。
また、体の酸性やアルカリ性のバランスを保ち、
栄養が運ばれやすくします。
さらに、細胞内に栄養素が入ったり、老廃物が出るのを助けたり、
異物への抗体の生成にも関与します。
ミネラルのほとんどは、ビタミンと一緒に働きます。
例えば、ビタミンCは鉄が一緒のときに、からだへの吸収がよくなります。
また、カルシウムはビタミンDがなければ吸収されることができません。
大量にとって余ったミネラルは、筋肉や骨に貯蔵されます。
しかし、長期にわたって大量にとり続けると、毒になることがあります。
現在、わかっているもので、無害とされているものはマグネシウムだけです。
※ミネラルの種類とその働き
ナトリウム
体液を正常に維持する
神経の刺激伝達を正常化する
血液とリンパ腺の健康を保つ
欠乏症:食欲減退、けいれん、疲労、感染症にかかりやすい
カルシウム
骨や歯の発達と強度を維持する
血液の正常な凝固作用をする
筋肉、神経の働きに関与する
欠乏症:骨粗鬆症、筋肉のけいれん、心臓の動悸、不眠症
マグネシウム
骨の成長の補助をする
体内の酸、アルカリのバランスを調整する
筋肉、神経の働きを正常化する
欠乏症:筋肉痛、情緒不安定、神経過敏症、低体温
鉄
赤血球の一部のヘモグロビンをつくる
ストレスや病気に対する抵抗力を高める
タンパク質の代謝に関係している
欠乏症:貧血、呼吸困難、便秘
亜鉛
ビタミンB群の正常な吸収と働きに関与している
酸素の働きを補助する
欠乏症:学習能力の低下、血液の循環不良、疲労、高コレステロール
マンガン
性ホルモンの合成に関与している
糖や脂質代謝に関与している
生殖機能を正常化する
欠乏症:運動失調症、めまい、難聴
セレン
免疫機構を促進する
病気に対する抵抗力を促進する
ガンの予防
欠乏症:白内障、膵臓の機能低下、感染症
銅
赤血球の生成に関係している
脂質代謝に関与している
欠乏症:うつ病、下痢、骨の軟化、呼吸異常
クロム
炭水化物の代謝に関与している
心臓血管病の予防
欠乏症:糖尿病、成長率低下
モリブデン
酸素の機能を活性化する
欠乏症:胃腸障害
ヨウ素
甲状腺ホルモンの合成に関与している
欠乏症:動脈硬化、甲状腺機能低下、肥満
カリウム
筋収縮、神経の刺激伝達に関与している
成長の正常化
欠乏症:血圧の低下、不整脈、呼吸器の障害、不眠症
リン
脳、神経、細胞膜の機能を維持する
骨や歯を形成する
細胞の成長を促進する
欠乏症:神経障害、疲労、骨の痛み、食欲減退
コバルト
ビタミンB12の一部を構成する物質
酵素を活性化する
欠乏症:貧血、うつ病、疲労、発育不全
健康工房 紀の郷
http://www.health-navi.net/
Posted by 健康工房 紀の郷 at
10:08
2008年06月18日
生命のコントローラー(4)~ビタミン・ミネラル(微量栄養素)
ミネラル
ミネラルとは?
ミネラル(Mineral)は、直訳すると鉱物、鉱石で、語源は鉱山(Mine)からきています。
このことから栄養学的に、ミネラルは生体金属元素と呼ばれていましたが、
非金属のヨウ素なども含まれていることもあり、
現在では、生体微量元素と定義されています。
人間の体を微細に考えると、地球上にある物質と同じように元素から出来ています。
その中でも、炭素、窒素、酸素、水素が人間のからだの大方を占めています。
その4種類の元素は、皮膚や体液、臓器の構成する要素として、
非常にたくさん使われており、多量元素と呼ばれています。
その多量元素の他に、カルシウムやリンがあり、量が少なく少量元素と呼ばれ、
さらに、カリウム、ナトリウム、マグネシウム、鉄などは、ほんのわずかしか存在しないために、
微量元素と呼ばれています。
人間のからだの成分は、酸素65%、炭素18%、水素10%、窒素3%で、
ほとんどを占めています。
さらに、カルシウム1.5%、リン1%をそれに合わせると、
人間のおよそ98%になります。
したがって、残りの2%が微量元素ということになります。
一般的にミネラルといえば、多量元素以外の少量元素や微量元素のことをいいます。
健康工房 紀の郷
http://www.health-navi.net/
Posted by 健康工房 紀の郷 at
09:46
2008年06月17日
生命のコントローラー(3)~ビタミン・ミネラル(微量栄養素)
ビタミンの働き
ビタミンは、体の中で重要な働きをする酵素と一緒に働きます。
したがって、ビタミンは助酵素や補酵素とも呼ばれ、
その働きはほとんど細胞内で行われています。
酵素はビタミンがなくても、かなり長い間、その働きを続けることは出来ますが、
しだいに酵素の反応速度は低下していきます。
さらに、人間の体では、病原菌に感染しやすくなったり、
毒物に影響を受けやすくなったりと、抵抗力が落ちてきます。
ビタミン不足の状態が続くと、酵素の働きが悪くなり、
細胞が死に、他の組織や器官にも徐々に影響を受け始めます。
反対に、ビタミンを必要以上にとった場合は、
尿として排泄されてしまうか、体内に貯蔵されます。
また、さらに多くとった場合は、毒になることもあります。
したがって、ビタミンの効果はすぐに現れるものではありませんが、
ビタミンは私達人間の体にとって大変重要なものです。
※ビタミンの種類とその働き
ビタミンA・・・脂溶性
皮膚や粘膜を丈夫に保ち、感染予防に効果がある。
暗い所での視力を正常に保つ。抗ガン・成長促進作用。
欠乏症:夜盲症、成長の鈍化、骨や歯の発育が悪くなる、細菌に対する抵抗力の低下。
ビタミンB1・・・水溶性
糖質をエネルギーに変える働き。
消化液の分泌を良くする。
神経の調節に関係する。
欠乏症:脚気、消化不良、便秘、神経機能減退、疲労、倦怠。
ビタミンB2・・・水溶性
脂質の代謝に必要で、皮膚や粘膜の生成に関わる。
細胞の再生、エネルギー代謝の促進。
欠乏症:成長停止、目の充血、口唇・口腔・鼻などのただれ。
ビタミンB6・・・水溶性
主にタンパク質と糖質の代謝に関係している。
神経伝達物質の生成に関わる。
免疫機能を正常に維持する。
アレルギーの予防。
欠乏症:貧血、皮膚炎、脂肪肝、神経過敏
ビタミンB12・・・水溶性
赤血球の育成(造血作用)
主にタンパク質と糖質の代謝に関係している。
神経伝達物質の生成に関わる。
免疫機能を正常に維持する。
欠乏症:悪性貧血、手足のしびれ・記憶障害等の神経症状、食欲不振、
ビタミンC・・・水溶性
細胞を健康に保ち、ガンなどを予防する。
毛細血管、歯、軟骨などを健康に保つ。
病気に対する抵抗力の増強。
副腎皮質ホルモンの生成、鉄の吸収に関与。
欠乏症:骨や歯が弱くなる、貧血、病気に対する抵抗力の減退。
ビタミンD・・・脂溶性
腸からのカルシウムの吸収を盛んにする。
紫外線にあたると皮膚でつくられる骨の発育に関係。
欠乏症:骨軟化症、乳児の骨の発達が悪くなる。
ビタミンE・・・脂溶性
血管壁を丈夫にし、動脈硬化を予防する。
老化防止に役立つ。
流産を防止する。
筋肉の機能を良くする。
欠乏症:筋肉の萎縮、生理活性の弱化、胎児の成長不全、感染症。
ビタミンK・・・脂溶性
血液凝固に関与している。
骨にカルシウムが沈着するのを助ける。
欠乏症:鼻血が出やすい、血が止まりにくい、胃の粘膜が弱くなる、骨が弱くなる。
ナイアシン・・・水溶性
皮膚を丈夫に保ち、神経系に関与している。
糖質・脂質の代謝に働く。
脳神経の働きを助ける。
血行を良くする。
欠乏症:頭痛、めまい、不安感、食欲不振。
葉酸・・・水溶性
赤血球を作るときに必要。
抗体の生産に働く。
発育を促す。
欠乏症:潰瘍になりやすい、抵抗力低下、神経過敏。
パントテン酸・・・水溶性
糖質・脂質・タンパク質の代謝に関係している。
副腎皮質ホルモンの合成に働く。
ストレスの抵抗力をつける。
免疫抗体の生産・解毒に働く。
欠乏症:感染症にかかりやすい、疲れやすい、動脈硬化を進める。
ビオチン・・・水溶性
糖質・脂質・タンパク質の代謝を助ける。
欠乏症:食欲不振、皮膚炎、脱毛、白髪になりやすい、疲労感。
健康工房 紀の郷
http://www.health-navi.net/
Posted by 健康工房 紀の郷 at
10:51
2008年06月09日
生命のコントローラー(2)~ミネラル・ビタミン(微量栄養素)
ビタミン
ビタミンとは?
ビタミンは、19世紀はじめの脚気(かっけ)の研究から発見されました。
そのとき発見された化学物質が「アミン」と呼ばれるもので、
「生命(Vita)に必要な「アミン(amine)ということで、ビタミン(Vitamine)と命名されました。
その後、必ずしもアミンを含むとは限らないことがわかり、
語尾のeを削ってVitamin(ビタミン)と改められました。
その後の研究で、ビタミンは人間を含めた全ての生物に、
微量でからだを調節することがわかりました。
19世紀はじめにビタミンA,B,Cが発見され、
その後は発見された順にアルファベットをつけ、命名されていきました。
また、中にはナイアシン、パントテン酸、葉酸など、
はじめから化学的な名称をつけられたものもありました。
ところが、ビタミンBは一旦命名されたものの、
実際には1種類ではなく、いくつかあることがわかり、
B の右下に番号をつけビタミンB1、B2・・・とされました。
その後、ビタミンでないことや、
化学的な名称でつけられたものと同じであることがわかったものが抜けていき、
現在では、B1、B2、B6、B12の4種類となりました。
また、ビタミンは脂溶性ビタミン(油に溶けるビタミン)と、
水溶性ビタミン(水に溶けるビタミン)にも、分類されています。
健康工房 紀の郷
http://www.health-navi.net/
Posted by 健康工房 紀の郷 at
10:12
2008年06月08日
生命のコントローラー(1)~ビタミン・ミネラル(微量栄養素)
生命のコントローラー
私達人間は、生きていくためにたくさんの栄養を取り入れる必要があります。
取り入れた栄養を利用して、人間は成長、運動などの生命活動を行っています。
一般的に、三大栄養素と呼ばれる炭水化物、脂質、タンパク質は、
人間にとって大量に摂取する必要があり、主にエネルギー源として利用されています。
一方、ビタミン、ミネラルという栄養素は非常に少ない量で有意義な働きをし、
微量栄養素と呼ばれています。
ビタミンは体内で起こっている化学反応をコントロールするために必要な有機化合物で、
ミネラルはからだの調節や一部をつくるために必要な元素です。
ビタミン、ミネラルは、エネルギー源の三大栄養素とは異なり、
生命活動を調節していくコントローラー(調節器)ともいうべき重要な役割を果たしています。
健康工房 紀の郷
http://www.health-navi.net/
Posted by 健康工房 紀の郷 at
10:48
2008年06月06日
子供のからだと脳と食生活(6)
骨をつくる栄養素
骨というとまずカルシウムを連想しますが、
カルシウムだけたくさんとっていれば丈夫な骨が出来るのでしょうか?
まず、骨格は何でできているのかというと、
カルシウムだけでなく、タンパク質やリン、マグネシウムなども使われています。
特にリンはカルシウムとほぼ同量使われていて、
骨の重要な構成部分となっています。
また、マグネシウムは、カルシウム、タンパク質、リンに続く骨の重要な成分で、
骨をつくる過程でも働いています。
骨の三大主要成分・・・カルシウム・タンパク質(コラーゲン)・リン
そして、カルシウムが腸管から吸収されるのを促すビタミンD、
骨にカルシウムを吸着させるビタミンK,
カルシウム定着の足場になるコラーゲンの生成に欠かせないビタミンC,
これらの栄養素の相互作用で骨は元気を保つことが出来ます。
また、成長期にビタミンAが不足すると、
骨や歯の形成が阻害され成長が悪くなります。
血液に重要なヘモグロビンの材料
骨の中心部である骨髄では、血液に重要なヘモグロビンがつくられています。
その材料としてタンパク質、鉄、銅などのミネラル類、
それにビタミンB6、B12、C、Eなどが必要です。
ひとつが多すぎても生育が悪くなる
カルシウムだけが多いと、骨がつくられる際に、
鉄やマグネシウムが使われにくくなることが動物実験の報告にもあり、
骨の生育が悪くなると考えられています。
また、カルシウムだけでなく、リンが多すぎても骨の生育を邪魔することになります。
最近の食品、特にインスタント麺、清涼飲料、合成酒、缶詰、ハムなどには
リンが多いので、偏食に注意しましょう。
いろいろな食材から種々の栄養素をとり、
ミネラルやビタミンのバランスを整えることが重要だといえます。
健康工房 紀の郷
http://www.health-navi.net/
骨というとまずカルシウムを連想しますが、
カルシウムだけたくさんとっていれば丈夫な骨が出来るのでしょうか?
まず、骨格は何でできているのかというと、
カルシウムだけでなく、タンパク質やリン、マグネシウムなども使われています。
特にリンはカルシウムとほぼ同量使われていて、
骨の重要な構成部分となっています。
また、マグネシウムは、カルシウム、タンパク質、リンに続く骨の重要な成分で、
骨をつくる過程でも働いています。
骨の三大主要成分・・・カルシウム・タンパク質(コラーゲン)・リン
そして、カルシウムが腸管から吸収されるのを促すビタミンD、
骨にカルシウムを吸着させるビタミンK,
カルシウム定着の足場になるコラーゲンの生成に欠かせないビタミンC,
これらの栄養素の相互作用で骨は元気を保つことが出来ます。
また、成長期にビタミンAが不足すると、
骨や歯の形成が阻害され成長が悪くなります。
血液に重要なヘモグロビンの材料
骨の中心部である骨髄では、血液に重要なヘモグロビンがつくられています。
その材料としてタンパク質、鉄、銅などのミネラル類、
それにビタミンB6、B12、C、Eなどが必要です。
ひとつが多すぎても生育が悪くなる
カルシウムだけが多いと、骨がつくられる際に、
鉄やマグネシウムが使われにくくなることが動物実験の報告にもあり、
骨の生育が悪くなると考えられています。
また、カルシウムだけでなく、リンが多すぎても骨の生育を邪魔することになります。
最近の食品、特にインスタント麺、清涼飲料、合成酒、缶詰、ハムなどには
リンが多いので、偏食に注意しましょう。
いろいろな食材から種々の栄養素をとり、
ミネラルやビタミンのバランスを整えることが重要だといえます。
健康工房 紀の郷
http://www.health-navi.net/
Posted by 健康工房 紀の郷 at
11:14
2008年06月02日
子供のからだと脳と食生活(5)
栄養素は相互作用で力を発揮する
脳のエネルギー
脳はブドウ糖と酸素を盛んに使っています。
そのためどちらが不足しても頭がぼうっとして働きません。
脳は体重比では50分の1ですが、最近になって、
脳・神経系が1日に使うエネルギーが全身の筋肉なみだということがわかってきたそうです。
(聖マリアンナ医大横浜西部病院 栄養部長 中村丁次氏、読売新聞平成10年5月12日)
ブドウ糖は体内貯蔵に限りがあり、
起床時などには血糖値が70mg程度まで下がっていることもあります。
そんなとき、脳はガス欠気味。
だから、常に糖質で補ってあげることが必要です。
「同じ糖質でも甘いものより吸収のゆっくりした穀類が好ましく、
コメだけで補うとしたら最低1日3回茶碗1杯ずつ食べる必要がある。
ビタミン、ミネラルなどの微量栄養素も、脳の働きに関わっている。
朝食を抜いたりすれば当然、頭の働きが鈍くなり、
精神的な部分でも様々な症状が出るはずだ。」
と指摘しています。
朝、ビタミン、ミネラルとブドウ糖を充分とれる朝食を食べさせることが、
最も基本的な「頭脳食」であると言えます。
記憶や神経の働きをよくするために
脳細胞の一種であるニューロンは、
いくつも互いにつながりあって連なる網の目の構造を作っています。
刺激は瞬時にこの網目の上を走り、伝えられていきます。
刺激は、ニューロンの中では電気信号として、
また、ニューロンとニューロンのつなぎ目では、一方のニューロンからもう一方へ向かって
神経伝達物質という化学物質が放出されることで、伝えられていきます。
アセチルコリンは、その神経伝達物質のひとつですが、
この物質は身体の中でコリンからつくられます。
コリンが血液で運ばれて、パントテン酸という物質の助けにより、
神経伝達物質アセチルコリンになります。
コリンは不飽和脂肪酸とリン酸と一緒になってレシチンをつくり、
細胞膜になりますが、神経にも重要です。
コリンが豊富だと、記憶力や神経の働きがよくなるため、
体の調節がよくなります。
コリン、あるいはレシチンが不足してくると、
神経の働きや細胞の力が衰え、全身がだるくなり、衰弱してきます。
コリンの一部はアミノ酸から作られているので、
タンパク質が不足するとコリン欠乏症になりやすくなります。
コリンは、レシチンとしてとるのがとりやすいので、
頭の中で情報のやり取りをスムーズに行うためには、
アセチルコリンを充分量つくるだけのレシチンを食べる必要があります。
また、DHAは記憶力や学習能力を高め、
脳をイキイキさせて、脳の若さを保ちます。
脳内の細胞には多くのDHAが構成成分として含まれています。
特に、記憶の中枢とされる海馬というところには、
高濃度のDHAが含まれています。
DHAはイワシ、サバ、サンマ、アジ、ウナギ、マグロなど、
いわゆる青魚に多く含まれますが、体内でもつくられます。
シュンギク、ダイコン、ハクサイ、ホウレンソウなどの葉と根に多く含まれる
αーリノレン酸から体内でDHAがつくられます。
知能指数を上昇させた
「知能指数で表された知能は、
その人のそのときの栄養状態、少なくとも柑橘類や、
その他のアスコルビン酸を含む食物の摂取状態によって、かなり変わる。
またアスコルビン酸で、機敏さも鋭敏さも向上する」
というのはあるビタミン研究者の発言です。
これは、幼稚園児から大学生まで350人に対し、
食事以外にビタミンCを100~150mg与えた実験結果によるものです。
アスコルビン酸とはビタミンCのことです。
いわゆる、頭の回転の遅い子供や、ぼんやりすることの多い子供達の状態は、
特にビタミンCで改善できると考えられています。
またビタミンCや葉酸などの11種類のビタミンと8種類のミネラルを与えて、
知恵遅れの子供達の知能指数を、8ヶ月で16も上昇させたという研究者の報告もあります。
脳へは、体内の血液の5分の1が流れ、
非常に多くの酸素や栄養素を消費しているので、
栄養のバランスに影響を受けやすいのです。
健康工房 紀の郷
http://www.health-navi.net/
脳のエネルギー
脳はブドウ糖と酸素を盛んに使っています。
そのためどちらが不足しても頭がぼうっとして働きません。
脳は体重比では50分の1ですが、最近になって、
脳・神経系が1日に使うエネルギーが全身の筋肉なみだということがわかってきたそうです。
(聖マリアンナ医大横浜西部病院 栄養部長 中村丁次氏、読売新聞平成10年5月12日)
ブドウ糖は体内貯蔵に限りがあり、
起床時などには血糖値が70mg程度まで下がっていることもあります。
そんなとき、脳はガス欠気味。
だから、常に糖質で補ってあげることが必要です。
「同じ糖質でも甘いものより吸収のゆっくりした穀類が好ましく、
コメだけで補うとしたら最低1日3回茶碗1杯ずつ食べる必要がある。
ビタミン、ミネラルなどの微量栄養素も、脳の働きに関わっている。
朝食を抜いたりすれば当然、頭の働きが鈍くなり、
精神的な部分でも様々な症状が出るはずだ。」
と指摘しています。
朝、ビタミン、ミネラルとブドウ糖を充分とれる朝食を食べさせることが、
最も基本的な「頭脳食」であると言えます。
記憶や神経の働きをよくするために
脳細胞の一種であるニューロンは、
いくつも互いにつながりあって連なる網の目の構造を作っています。
刺激は瞬時にこの網目の上を走り、伝えられていきます。
刺激は、ニューロンの中では電気信号として、
また、ニューロンとニューロンのつなぎ目では、一方のニューロンからもう一方へ向かって
神経伝達物質という化学物質が放出されることで、伝えられていきます。
アセチルコリンは、その神経伝達物質のひとつですが、
この物質は身体の中でコリンからつくられます。
コリンが血液で運ばれて、パントテン酸という物質の助けにより、
神経伝達物質アセチルコリンになります。
コリンは不飽和脂肪酸とリン酸と一緒になってレシチンをつくり、
細胞膜になりますが、神経にも重要です。
コリンが豊富だと、記憶力や神経の働きがよくなるため、
体の調節がよくなります。
コリン、あるいはレシチンが不足してくると、
神経の働きや細胞の力が衰え、全身がだるくなり、衰弱してきます。
コリンの一部はアミノ酸から作られているので、
タンパク質が不足するとコリン欠乏症になりやすくなります。
コリンは、レシチンとしてとるのがとりやすいので、
頭の中で情報のやり取りをスムーズに行うためには、
アセチルコリンを充分量つくるだけのレシチンを食べる必要があります。
また、DHAは記憶力や学習能力を高め、
脳をイキイキさせて、脳の若さを保ちます。
脳内の細胞には多くのDHAが構成成分として含まれています。
特に、記憶の中枢とされる海馬というところには、
高濃度のDHAが含まれています。
DHAはイワシ、サバ、サンマ、アジ、ウナギ、マグロなど、
いわゆる青魚に多く含まれますが、体内でもつくられます。
シュンギク、ダイコン、ハクサイ、ホウレンソウなどの葉と根に多く含まれる
αーリノレン酸から体内でDHAがつくられます。
知能指数を上昇させた
「知能指数で表された知能は、
その人のそのときの栄養状態、少なくとも柑橘類や、
その他のアスコルビン酸を含む食物の摂取状態によって、かなり変わる。
またアスコルビン酸で、機敏さも鋭敏さも向上する」
というのはあるビタミン研究者の発言です。
これは、幼稚園児から大学生まで350人に対し、
食事以外にビタミンCを100~150mg与えた実験結果によるものです。
アスコルビン酸とはビタミンCのことです。
いわゆる、頭の回転の遅い子供や、ぼんやりすることの多い子供達の状態は、
特にビタミンCで改善できると考えられています。
またビタミンCや葉酸などの11種類のビタミンと8種類のミネラルを与えて、
知恵遅れの子供達の知能指数を、8ヶ月で16も上昇させたという研究者の報告もあります。
脳へは、体内の血液の5分の1が流れ、
非常に多くの酸素や栄養素を消費しているので、
栄養のバランスに影響を受けやすいのです。
健康工房 紀の郷
http://www.health-navi.net/
Posted by 健康工房 紀の郷 at
10:57
2008年06月01日
子供のからだと脳と食生活(4)
製造過程でなくなるビタミンB1
次に考えられる問題はビタミンB1の不足です。
特に高校生にビタミンB1不足が多くなっています。
ビタミンB1は糖質代謝に必要な栄養素で、
自然界の植物は必ずビタミンB1を含有しています。
しかし、白米、精白粉、白砂糖、アルコールは、
みなその製造過程でB1を取り去られてしまっています。
ましてインスタント食品ばかりの食事をしていれば、
B1不足になっても不思議ではありません。
ビタミンB1は体内に蓄えておくことができないビタミンです。
毎日適切な量をとる必要があります。
ちなみに精白度の高い穀物は、ビタミンだけでなくミネラルも取り去られています。
たとえば、精白後のマグネシウムは米で7割減、小麦で9割減にもなります。
凶暴な少年達に不足していた栄養素
80年代にアメリカの少年院で、入所者8千人の食事から菓子や炭酸飲料を除き、
新鮮な野菜、果物、全粒粉パンを与えたら、暴力沙汰や反抗などが半減し、
また別の入所者300人の食事を分析すると、
凶暴な少年達は、ビタミンB群、鉄、亜鉛など、
穀類の胚芽やふすま、新鮮な野菜や果物に多い栄養素が不足だったといいます。
本能のままに食べていては栄養のバランスが取れない
かつて精製食品や加工食品がなかった頃は、
食べたいものを食べたいだけ食べても、タンパク質やビタミン、ミネラルは摂れました。
自然界ではうまみはタンパク質のサイン、甘味は糖質のサインというように、
それらのサインを基準にして食べていれば、
自然に栄養素のバランスもとれていたのです。
人間はエネルギー源である油、糖、でんぷんを本能的に好みますが、
油だけ、砂糖だけ、でんぷんだけといった食品からは、
タンパク質やビタミン、ミネラルはとれません。
現在ではうま味だけ、甘味だけ、油脂だけを取り出し、
栄養成分があまり含まれていないものに加える、
加工食品が作られるようになりましたから、
本能的に美味しいと感じるものだけを食べていると、
栄養バランスを崩してしまいます。
例えば、動物性タンパク質からとり出したうま味と、食塩とを、
エネルギー以外の栄養素がほとんどない加工食品に付加したものの代表がインスタントラーメンです。
※参考
ビタミンB1
ビタミンB1不足によるもので有名なのは脚気(かっけ)です。
脚気になると、足を中心にだるく、疲れやすくなり、
動悸、息切れ、手足のしびれ、むくみ、食欲不振などの症状があらわれます。
また、憂鬱、イライラ、気難しく消極的で不安定な精神状態に陥ります。
ビタミンB!は、
「神経炎ビタミン」、「精神ビタミン」ともいわれます。
不足した場合、心の症状が先に出て、体の症状のほうが後から出ることが、
実験によってわかりました。
ですから、栄養欠乏は体の症状に現れると思っていると、
B1欠乏を見落とすことになりかねません。
またブドウ糖は、脳をはじめ身体のエネルギー源ですが、
エネルギーを作り出すとき、ビタミンB1が不足すると、
ブドウ糖は不完全燃焼を起こして、乳酸になってしまいます。
乳酸とは有名な疲労物質です。
この乳酸もまた、
肩こりを起こしたり、頭を重くしイライラさせたり、血液を酸性にしてしまいます。
この状態が長く続くと、
酸を中和するために骨や歯のカルシウムまでが動員されます。
このカルシウムも精神を安定させ、ストレスから守る働きがあるので、
不足しないようにする必要があります。
健康工房 紀の郷
http://www.health-navi.net/
1粒に、腸内細菌コッカス菌101株、302株が約437億個、
100種類の食物と、13種類のビタミン、12種類のミネラルが
ギュッと詰まっています。
コッカスプレンテイー100
次に考えられる問題はビタミンB1の不足です。
特に高校生にビタミンB1不足が多くなっています。
ビタミンB1は糖質代謝に必要な栄養素で、
自然界の植物は必ずビタミンB1を含有しています。
しかし、白米、精白粉、白砂糖、アルコールは、
みなその製造過程でB1を取り去られてしまっています。
ましてインスタント食品ばかりの食事をしていれば、
B1不足になっても不思議ではありません。
ビタミンB1は体内に蓄えておくことができないビタミンです。
毎日適切な量をとる必要があります。
ちなみに精白度の高い穀物は、ビタミンだけでなくミネラルも取り去られています。
たとえば、精白後のマグネシウムは米で7割減、小麦で9割減にもなります。
凶暴な少年達に不足していた栄養素
80年代にアメリカの少年院で、入所者8千人の食事から菓子や炭酸飲料を除き、
新鮮な野菜、果物、全粒粉パンを与えたら、暴力沙汰や反抗などが半減し、
また別の入所者300人の食事を分析すると、
凶暴な少年達は、ビタミンB群、鉄、亜鉛など、
穀類の胚芽やふすま、新鮮な野菜や果物に多い栄養素が不足だったといいます。
本能のままに食べていては栄養のバランスが取れない
かつて精製食品や加工食品がなかった頃は、
食べたいものを食べたいだけ食べても、タンパク質やビタミン、ミネラルは摂れました。
自然界ではうまみはタンパク質のサイン、甘味は糖質のサインというように、
それらのサインを基準にして食べていれば、
自然に栄養素のバランスもとれていたのです。
人間はエネルギー源である油、糖、でんぷんを本能的に好みますが、
油だけ、砂糖だけ、でんぷんだけといった食品からは、
タンパク質やビタミン、ミネラルはとれません。
現在ではうま味だけ、甘味だけ、油脂だけを取り出し、
栄養成分があまり含まれていないものに加える、
加工食品が作られるようになりましたから、
本能的に美味しいと感じるものだけを食べていると、
栄養バランスを崩してしまいます。
例えば、動物性タンパク質からとり出したうま味と、食塩とを、
エネルギー以外の栄養素がほとんどない加工食品に付加したものの代表がインスタントラーメンです。
※参考
ビタミンB1
ビタミンB1不足によるもので有名なのは脚気(かっけ)です。
脚気になると、足を中心にだるく、疲れやすくなり、
動悸、息切れ、手足のしびれ、むくみ、食欲不振などの症状があらわれます。
また、憂鬱、イライラ、気難しく消極的で不安定な精神状態に陥ります。
ビタミンB!は、
「神経炎ビタミン」、「精神ビタミン」ともいわれます。
不足した場合、心の症状が先に出て、体の症状のほうが後から出ることが、
実験によってわかりました。
ですから、栄養欠乏は体の症状に現れると思っていると、
B1欠乏を見落とすことになりかねません。
またブドウ糖は、脳をはじめ身体のエネルギー源ですが、
エネルギーを作り出すとき、ビタミンB1が不足すると、
ブドウ糖は不完全燃焼を起こして、乳酸になってしまいます。
乳酸とは有名な疲労物質です。
この乳酸もまた、
肩こりを起こしたり、頭を重くしイライラさせたり、血液を酸性にしてしまいます。
この状態が長く続くと、
酸を中和するために骨や歯のカルシウムまでが動員されます。
このカルシウムも精神を安定させ、ストレスから守る働きがあるので、
不足しないようにする必要があります。
健康工房 紀の郷
http://www.health-navi.net/
1粒に、腸内細菌コッカス菌101株、302株が約437億個、
100種類の食物と、13種類のビタミン、12種類のミネラルが
ギュッと詰まっています。
コッカスプレンテイー100
Posted by 健康工房 紀の郷 at
09:51