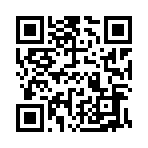2009年04月25日
こんなあなたは「肌さび」がたまっています
肌のクスミ
肌さびがたまると、細胞の新陳代謝が鈍り、肌の再生サイクルである
「ターンオーバー」が乱れやすくなり、古い角質細胞が表皮にいつまでも残るので、
肌がくすんで見えるようになります。
シミやシワが多い
肌さびの影響で細胞が老化すると保水力が低下し、
シミの原因であるメラニン色素が沈着しやすくなるので、
シミやシワが多くなります。
年齢よりも老けて見える
老化は避けられません。
でも、同世代の人よりもふけて見えるのは、
細胞が肌さびの影響を受けている証拠です。
肌が乾燥する
肌の細胞の配列が乱れ、保水力が低下して起こる肌荒れも、
肌さびによる影響です。
肌が乾燥するとさらに肌さびがすすみ悪循環です。
たるみが気になる
肌さびがたまると肌のハリを支えるコラーゲンがダメージを受け、
たるみもひどくなります。
その影響で小鼻のまわりやほおの毛穴もめだつようになります。
ニキビが治りにくい
活性酸素は、ニキビの原因アクネ菌を退治しますが、
大量発生すると、逆に炎症がひどくなりニキビが治りにくくなります。
肌さびがたまると、細胞の新陳代謝が鈍り、肌の再生サイクルである
「ターンオーバー」が乱れやすくなり、古い角質細胞が表皮にいつまでも残るので、
肌がくすんで見えるようになります。
シミやシワが多い
肌さびの影響で細胞が老化すると保水力が低下し、
シミの原因であるメラニン色素が沈着しやすくなるので、
シミやシワが多くなります。
年齢よりも老けて見える
老化は避けられません。
でも、同世代の人よりもふけて見えるのは、
細胞が肌さびの影響を受けている証拠です。
肌が乾燥する
肌の細胞の配列が乱れ、保水力が低下して起こる肌荒れも、
肌さびによる影響です。
肌が乾燥するとさらに肌さびがすすみ悪循環です。
たるみが気になる
肌さびがたまると肌のハリを支えるコラーゲンがダメージを受け、
たるみもひどくなります。
その影響で小鼻のまわりやほおの毛穴もめだつようになります。
ニキビが治りにくい
活性酸素は、ニキビの原因アクネ菌を退治しますが、
大量発生すると、逆に炎症がひどくなりニキビが治りにくくなります。
ご家族の健康生活を応援する
2009年04月18日
肌さびが肌にダメージを与える
肌のうるおいを守ってきめを整える皮脂や、
表皮の細胞と細胞をくっつけている細胞間脂質が活性酸素により、
いちばん酸化されやすいところです。
これらの脂質が酸化されると過酸化資質という物質に変化します。
この過酸化脂質という物質がいわゆる「肌さび」です。
過酸化脂質は表皮の細胞はもちろん、
メラニン色素を生成するメラノサイトを刺激したり、
肌の奥のコラーゲンにダメージを与えるほど強力です。
活性酸素の影響を受けても、若い頃は、抗酸化物質やSOD酵素の力が強く、
強力にはね返すので、過酸化脂質はそれほどつくられません。
でも、30歳を過ぎると、抗酸化力が低下し、徐々に肌さびがたまり始め、
その影響で肌の衰えが目立つようになります。
最近では、食生活の乱れや不規則な生活習慣により、
10代~20代の人でも、体の抗酸化力が弱く、
活性酸素の影響を受けやすい人も増えています。
表皮の細胞と細胞をくっつけている細胞間脂質が活性酸素により、
いちばん酸化されやすいところです。
これらの脂質が酸化されると過酸化資質という物質に変化します。
この過酸化脂質という物質がいわゆる「肌さび」です。
過酸化脂質は表皮の細胞はもちろん、
メラニン色素を生成するメラノサイトを刺激したり、
肌の奥のコラーゲンにダメージを与えるほど強力です。
活性酸素の影響を受けても、若い頃は、抗酸化物質やSOD酵素の力が強く、
強力にはね返すので、過酸化脂質はそれほどつくられません。
でも、30歳を過ぎると、抗酸化力が低下し、徐々に肌さびがたまり始め、
その影響で肌の衰えが目立つようになります。
最近では、食生活の乱れや不規則な生活習慣により、
10代~20代の人でも、体の抗酸化力が弱く、
活性酸素の影響を受けやすい人も増えています。
ご家族の健康生活を応援する
2009年04月12日
活性酸素と肌の老化(肌さび)
私達が生きていくために、無くてはならない大切な酸素。
でも酸素には、釘を錆びつかせてボロボロにするように、
物を酸化させて変質させる困った働きがあります。
この酸化を起こしやすい物質は「フリーラジカル」と呼ばれ、
なかでも強い攻撃力を持っているのが活性酸素です。
活性酸素は呼吸によってエネルギーをつくるときにも生み出されますが、
それ以上に問題になるのが、紫外線や汚れた空気、電磁波、過度のスポーツ、
野菜不足の食生活など、自分を取り巻く環境や生活の影響です。
これらの影響を受ければ受けるほど活性酸素はどんどん体内でつくられます。
そして、その影響で肌の細胞がダメージを受け
シミ、シワが増え、ニキビなどが治りにくくなるのです。
活性酸素の研究では世界的権威の丹羽耕三博士は、
アトピー性皮膚炎などの肌のトラブルも活性酸素が原因と
国内外の学会で発表しています。
でも酸素には、釘を錆びつかせてボロボロにするように、
物を酸化させて変質させる困った働きがあります。
この酸化を起こしやすい物質は「フリーラジカル」と呼ばれ、
なかでも強い攻撃力を持っているのが活性酸素です。
活性酸素は呼吸によってエネルギーをつくるときにも生み出されますが、
それ以上に問題になるのが、紫外線や汚れた空気、電磁波、過度のスポーツ、
野菜不足の食生活など、自分を取り巻く環境や生活の影響です。
これらの影響を受ければ受けるほど活性酸素はどんどん体内でつくられます。
そして、その影響で肌の細胞がダメージを受け
シミ、シワが増え、ニキビなどが治りにくくなるのです。
活性酸素の研究では世界的権威の丹羽耕三博士は、
アトピー性皮膚炎などの肌のトラブルも活性酸素が原因と
国内外の学会で発表しています。
ご家族の健康生活を応援する
2009年04月07日
旬の野菜が食べたい!~オクラ~
タンパク質分解酵素が含まれるので、
オクラを生で利用すると魚や肉の消化を助けます。
食物繊維も豊富。
さらにミネラル、ビタミン類がバランスよく含まれていますから、
不足しがちな栄養素を補う副菜として光ります。
ポイント
■タンパク質の消化を助けるので、魚や肉と一緒に食べるとよい。
■タンパク質分解酵素を活用したいときは、酵素は熱に弱いので、
さっと熱を通す程度がよい。
■成人病やがん予防に役立つ栄養素がそろった優れた野菜です。
栄養
■一般に、野菜はビタミン、ミネラルなどいわゆる微量栄養素の供給源として大事なものです。
その点、オクラはなかなかの優れものです。
キュウリと比べると不足しがちな栄養素が、全て勝っているのです。
オクラは茹でて食べることが多いですが、ビタミンCがやや減少するものの、
茹でることによる栄養損失はあまり気にかけなくてもよいでしょう。
一度にあまりたくさん食べる素材ではないとはいえ、他の材料に不足するものを充分に補える、
存在感のある野菜のひとつといえるでしょう。
■ミネラルを見ても、リンは60mgでカルシウムとのバランスがよく、
カリウム、亜鉛の含有量も少なくありません。
■もうひとつ、オクラは粘りがあるのが特徴です。
この粘りはムチンという物質で、タンパク質と糖が結合したものです。
高分子が絡まりあったために粘るのです。
このムチンの中には、タンパク質分解酵素が存在し、魚や肉などの消化を助ける働きがあります。
■生のオクラを切っておくと黒ずみます。
これはオクラに含まれているポリフェノール化合物によるものです。
この物質には、がん予防の効果も認められています。
調理のコツ
タンパク質分解酵素は加熱に弱く60℃で効力を失います。
オクラには、うぶ毛があるので、水洗いしたあと塩をふり、
もんでから茹でますが、たっぷりの沸騰した湯にいれ、
表面の色がさえる程度にサッとゆで、氷水にとって急速に冷まします。
こうすることで色も美しく保てます。
オクラを生で利用すると魚や肉の消化を助けます。
食物繊維も豊富。
さらにミネラル、ビタミン類がバランスよく含まれていますから、
不足しがちな栄養素を補う副菜として光ります。
ポイント
■タンパク質の消化を助けるので、魚や肉と一緒に食べるとよい。
■タンパク質分解酵素を活用したいときは、酵素は熱に弱いので、
さっと熱を通す程度がよい。
■成人病やがん予防に役立つ栄養素がそろった優れた野菜です。
栄養
■一般に、野菜はビタミン、ミネラルなどいわゆる微量栄養素の供給源として大事なものです。
その点、オクラはなかなかの優れものです。
キュウリと比べると不足しがちな栄養素が、全て勝っているのです。
オクラは茹でて食べることが多いですが、ビタミンCがやや減少するものの、
茹でることによる栄養損失はあまり気にかけなくてもよいでしょう。
一度にあまりたくさん食べる素材ではないとはいえ、他の材料に不足するものを充分に補える、
存在感のある野菜のひとつといえるでしょう。
■ミネラルを見ても、リンは60mgでカルシウムとのバランスがよく、
カリウム、亜鉛の含有量も少なくありません。
■もうひとつ、オクラは粘りがあるのが特徴です。
この粘りはムチンという物質で、タンパク質と糖が結合したものです。
高分子が絡まりあったために粘るのです。
このムチンの中には、タンパク質分解酵素が存在し、魚や肉などの消化を助ける働きがあります。
■生のオクラを切っておくと黒ずみます。
これはオクラに含まれているポリフェノール化合物によるものです。
この物質には、がん予防の効果も認められています。
調理のコツ
タンパク質分解酵素は加熱に弱く60℃で効力を失います。
オクラには、うぶ毛があるので、水洗いしたあと塩をふり、
もんでから茹でますが、たっぷりの沸騰した湯にいれ、
表面の色がさえる程度にサッとゆで、氷水にとって急速に冷まします。
こうすることで色も美しく保てます。
ご家族の健康生活を応援する
Posted by 健康工房 紀の郷 at
15:58
2009年04月02日
体温が平熱を保つしくみ
私達の体は、36.5℃前後に保たれていなければ生きていられません。
この体温は、体の中でつくられる熱と、体外へ逃がされている熱との
バランスによって保たれています。
熱は、摂取した食べ物の栄養素が消化・吸収され、
肝臓や筋肉その他で代謝を受け、
最終的には二酸化炭素に分解される過程で作られます(科学的な仕組み)。
一方、熱を体外へ放射する仕組みは輻射、伝導、対流及び水分蒸散によっています。
(物理的な仕組み)
服を着ればきるほど温かいのは、皮膚から服へ、服から服へ、服から壁へと
熱の放射が複雑になるため、逆に体温の放散を阻害しているためです。
この科学的な熱産生と物理学的な熱放散のバランスをとり、
体温を36.5℃に保たせているのは、大脳の中の視床下部の前後にある熱産生の
中枢と熱放散の中枢、及びその2つを統括している体温調節中枢の働きによります。
これが、エアコンを36.5℃にセットしたときのように働いていることになります。
つまり、体温が36.5℃以下になると熱産生の中枢が働き、
36.5℃以上になると熱放散の中枢が働いてバランスをとるのです。
このように、人間の体は、各臓器から細胞にいたるまで
それぞれがバランスをとって成り立っています。
そのバランスを崩さないよう日頃からの心がけが大切です。
この体温は、体の中でつくられる熱と、体外へ逃がされている熱との
バランスによって保たれています。
熱は、摂取した食べ物の栄養素が消化・吸収され、
肝臓や筋肉その他で代謝を受け、
最終的には二酸化炭素に分解される過程で作られます(科学的な仕組み)。
一方、熱を体外へ放射する仕組みは輻射、伝導、対流及び水分蒸散によっています。
(物理的な仕組み)
服を着ればきるほど温かいのは、皮膚から服へ、服から服へ、服から壁へと
熱の放射が複雑になるため、逆に体温の放散を阻害しているためです。
この科学的な熱産生と物理学的な熱放散のバランスをとり、
体温を36.5℃に保たせているのは、大脳の中の視床下部の前後にある熱産生の
中枢と熱放散の中枢、及びその2つを統括している体温調節中枢の働きによります。
これが、エアコンを36.5℃にセットしたときのように働いていることになります。
つまり、体温が36.5℃以下になると熱産生の中枢が働き、
36.5℃以上になると熱放散の中枢が働いてバランスをとるのです。
このように、人間の体は、各臓器から細胞にいたるまで
それぞれがバランスをとって成り立っています。
そのバランスを崩さないよう日頃からの心がけが大切です。
ご家族の健康生活を応援する
Posted by 健康工房 紀の郷 at
14:50