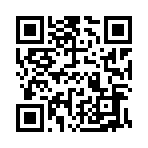2009年02月25日
ウコンの成分とその働き

■ウコンの成分とその働き
☆フラボノイド類
顕花植物中に存在して、抗出血性ビタミンPの作用をします。
ビタミンPというのは、毛細血管の壁を緻密にする働きがあるので、
血中から、タンパク質やビタミンCなどが、血管の外に抜け出し、
尿などに流れ出してしまうのを防いでいます。
ですから、ビタミンCやビタミンPが不足すると歯茎から出血したりします。
☆アズレン
炎症や潰瘍を治す作用、胃液のペプシンを抑える作用がありますから、
アフタ性口内炎、胃・十二指腸潰瘍などの治療薬の成分として使われます。
☆カンファー
神経の興奮作用、強心作用を持つ精油成分。
☆シネオール
健胃作用、殺菌、防腐作用に優れた効果を持つ物質です。
☆マグネシウム
ビタミンCの代謝に必要なだけでなく、カルシウム、ナトリウム、リンの代謝を
潤滑にしますし、各種の酵素の働きを補助する上でも極めて重要です。
マグネシウムの60%以上は骨格中にあり、
その他、筋肉、脳、神経などに分布しています。
筋肉中には、マグネシウムの方が、カルシウムより多く含まれています。
さらに、血液中の糖をエネルギーに変えたり、
ストレスの解消に一役買うなど、不可欠な成分です。
☆カルシウム
主な働きは、神経の伝達に関わりますので、
自律神経失調症や不眠、イライラ感などを起こします。
また、ウコンにはこの他、カリウムやタンニン、タンパク質、鉄、リンなどの
ミネラルが豊富に含まれています。
クルクミンたっぷりウコン
http://www.health-navi.net/ichiran/mineraru/ukon.htm
ご家族の健康生活を応援する
健康工房 紀の郷
Posted by 健康工房 紀の郷 at
10:59
│クルクミンたっぷりウコン
2009年02月23日
ウコンの主成分はクルクミン
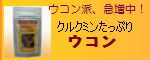
国立衛星研究所などの分析結果からも、ウコンには、
クルクミン、フラボノイド、アズレン、カンファー、ミネオールなど
数々の有効成分が含まれていることが明らかにされています。
クルクミンは、肝臓の働きを強化しますし、
胆汁の分泌を促す作用と利尿作用があります。
肝臓は沈黙の臓器といわれ、なかなか自覚症状があらわれません。
現れたときにはすでに時遅しといわれています。
肝臓の病気には、急性ウイルス肝炎、慢性肝炎、脂肪肝、肝硬変、
肝臓ガンなどがありますが、いずれも特効薬がないので治療に困る病気です。
常日頃から、アルコールを多飲する人などは、特に注意しなければなりません。
肝臓は、体の化学工場といわれるほど、実に様々な働きをする臓器です。
昔から非常に大切なことを「肝腎(心)かなめ」というくらい、
重要な内蔵が肝臓なのです。
その働きは「化学工場」らしく、500種以上もあり、
その主なものは、
①胆汁の分泌・・・胆汁は、一時的に胆のうに貯えられ、濃縮されますが、
腸に分泌され、特に脂肪の消化を促進し、ビタミンの代謝に働きます。
②栄養分の貯蔵と代謝
③解毒作用
があります。
クルクミンたっぷりウコン
http://www.health-navi.net/ichiran/mineraru/ukon.htm
健康家族を応援する
健康工房 紀の郷
健康工房 紀の郷
Posted by 健康工房 紀の郷 at
10:58
│クルクミンたっぷりウコン
2009年02月18日
花粉症対策はコレだ!

三共ライフテック㈱は、有胞子性乳酸菌の花粉症に対する効果を検討するため、
スギ花粉症を有する成人を対象にした試験を実施しました。
その結果、有胞子性乳酸菌として初めて、
花粉症の症状を改善する効果を有することが示唆されました。
有胞子性乳酸菌は、花粉症、気管支喘息、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎
または、アレルギー性結膜炎に対して有効であるが、
対称疾患としてさらに好ましいのは、花粉症、アレルギー性鼻炎及びアレルギー性結膜炎であり、
最も好ましいのは、その期間が比較的長いと考えられ、
継続的な投与が必要な、花粉症であるとその効果について述べています
有胞子乳酸菌は胞子を形成する乳酸菌であり、
乾燥状態、熱及び酸に非常に強く、
ヒトに経口投与された場合でも胃酸や胆汁で死滅せずに腸に到達し、
腸内で発芽、増殖して乳酸を産生する。
抗アレルギー剤の有効成分である有胞子乳酸菌としては、
市販の有胞子乳酸菌を用いることができる。
例えば、三共ライフテック㈱の「ラクリス-S」、「ラクリス-S顆粒」などがそれである。
このように、有胞子性乳酸菌「ラクリス-S」を用いたサプリメントが
花粉症に最適な乳酸菌として今注目を集めています。
ぜひ一度お試しください。
生きた乳酸菌 ラクリス-S 配合
秘伝 梅肉黒酢 ラクリア
ヒト由来腸内乳酸菌配合
コッカス プレンティー100
青みかんパワー
アレルエイドサプリ 青みかんの奇跡
健康家族を応援する
健康工房 紀の郷
Posted by 健康工房 紀の郷 at
10:06
2009年02月12日
青みかん・・・抗アレルギー作用と抗酸化作用のW効果

アレルギーは、激しい症状で教えてくれる生体防御反応です。
人体に侵入してきたアレルギーを起こす原因となる物質(抗原、アレルゲン)を排除し、
体を守るために働くのが”免疫”システムです。
ところが素直に排出しないで、一旦そのアレルゲンの侵入を激しい症状(痒み、セキ、鼻水など)で
教えてくれるのがアレルギーの特徴です。
青みかんの成分、ヘスペリジンは、痒み、くしゃみ、鼻水、涙目などのアレルギー症状を引き起こす
ヒスタミンなど化学物質の分泌を抑制します。
しかし、激しいアレルギー症状の元凶となる活性酸素を除去しなくては、症状沈静化や治癒は望めません。
活性酸素の除去には、抗酸化物質による抗酸化作用の力が必要です。
青みかんには、フラボノイドの一種であるノビレチン、食物繊維、香気成分、精油成分などの
抗酸化物質が多種・多様に含まれています。
抗酸化作用に優れた天然の青みかんを丸ごと使用することにより、ヘスペリジンとの相乗効果を発揮します。
青みかんのこの素晴らしい力を、ヘスペリジン単体に置き換えることはできないのです。
つまり、ホールフーズ=物全体、青みかんを丸ごと使用することによって、抗アレルギー作用と
抗酸化作用のW効果を期待できるのです。
花粉対策はお早めに・・・花粉の飛散が始まりました。
↓ ↓ ↓
アレルエイドサプリ 青みかんの遺跡
ご家族の健康を応援する
健康工房 紀の郷
Posted by 健康工房 紀の郷 at
15:10
2009年02月10日
アレルギーと免疫・・・花粉症はなぜ起こる?

花粉症がアレルギー反応のひとつであることは、ご存知の通り。
このアレルギー、意外なことに健康な身体を保つために欠かせない免疫と、体内での仕組みは同じなのです。
人体には、外部から侵入してくる異物に対して、その物質を排除する働きがあります。
外部から侵入してきた物質(抗原)に抵抗する物質(抗体)を作って体を守ろうとしますが、
抗体が一定量になったとき、同じ抗原が侵入してくると、
その抗原が抗体と結びつきそれまでと違った反応を示すようになります。
この反応が身体にとって都合よく働く場合を「免疫」といいます。
人体は、外から侵入してきた抗原に対し抗体を作って自分を守ろうとしますが、
花粉症の場合、花粉という抗原に対し、IgE抗体と呼ばれるアレルギー抗体を作って反応します。
IgE抗体は、花粉症のほかにもアトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、気管支喘息などと深くかかわっています。
IgE抗体は、原因となる花粉との接触を何度か繰り返すうちに体内に蓄積されてゆきます。
この蓄積が一定の水準に達したとき、発病する条件が整った状態になり、
この状態で再度、花粉に接触すると抗原とIgE抗体が結びついて花粉症の症状があらわれます。
IgE抗体が蓄積されつつある人でも、一定の水準に達していなければ症状は出ません。
いわば花粉症予備軍の人たちですね。
しかし、このまま花粉との接触を続けていれば、いつか花粉症を発症してしまいます。
ですので、すでにIgE抗体が体内の水準に達している人は、症状の程度の差はあっても、
花粉飛散量に関係なく発症してしまいます。
花粉対策 アレルエイドサプリ 青みかんの奇跡
ご家族の健康を応援する
健康工房 紀の郷
Posted by 健康工房 紀の郷 at
12:17
2008年10月29日
カレー(ウコン)がアルツハイマーの予防と治療に?-2
和歌山生まれ、和歌山発の

アルツハイマー病の患者の脳細胞に、アミロイド・ベータが蓄積してできる
アミロイド・ベータ斑はアルツハイマー病の発病と症状に関係しているという
研究者もいるようです。
6人のアルツハイマー病患者と、3人の健康な患者の血液サンプルを使用して、
研究チームは、マクロファージと呼ばれる免疫細胞を単離しました。
マクロファージは、ベータアミロイドを含む廃棄物を取り込みながら、
脳と身体を旅行する免疫システムの「パックマン」です。
研究チームは、24時間の細胞培養で、
クルクミンから得られた薬でマクロファージをテストしました。
6人のアルツハイマー病の患者のうち3人から採取した
マクロファージをテストして、クルクミンで処理していないマクロファージと比べて、
廃棄物の取入れと処理の改善を示しました。
健康な人から採取したマクロファージは、
すでに効果的にアミロイド・ベータを取り除いていますが、
クルクミンを加えても変化は見られませんでした。
クルクミンは、アルツハイマー病患者の50%で、
免疫細胞によるアミロイド・ベータの処理を改善しました。
これらの初めての発見は、クルクミンは特定のアルツハイマー病患者の
免疫システムの働きを高めるのを助けることを示しました、
と研究者は述べています。
健康工房 紀の郷
http://www.health-navi.net/
Posted by 健康工房 紀の郷 at
09:48
2008年10月28日
カレー(ウコン)がアルツハイマーの予防と治療に?
和歌山生まれの

カレーがアルツハイマーの予防と治療に役立つって本当?
カレーに含まれる化学物質は、
アルツハイマー病の脳にできるシミを掃除する
免疫システムを助けるかもしれません。
痴呆、認知症の原因として最も多いのがアルツハイマーです。
記憶、思考、判断など知的機能が、徐々に失われていきます。
日常の生活行動が正常にできなくなります。
現状では、進行を遅らせ症状を緩和させるしか方法がなく、予防が大切です。
研究者は、カレー粉に含まれるクルクミンが、
免疫システムがアミロイド・ベータ斑を脳から取り除くのを助けることを発見しました。
アミロイド・ベータ斑はアルツハイマーの特徴的な兆候の一つです。
カレー粉の主な材料のターメリック(ウコン)の有効成分のクルクミンは、
抗炎症作用と活性酸素のダメージを防ぐ抗酸化作用の特性が知られています。
抗ガン作用も報告されています。
続きは次回。
健康工房 紀の郷
http://www.health-navi.net/
Posted by 健康工房 紀の郷 at
10:27
2008年10月27日
金時ショウガでお手軽冷え対策
和歌山生まれの

金時ショウガの有効成分は普通のショウガの約4倍!
冷え性の方にはとってもお手軽な冷え対策の食品です。
ショウガは、薬味や香辛料として料理の味をひきたたせます。
また、気の流れをよくし体に活力を与えてくれる貴重な植物として
何千年も前のインド古代医学でも愛用されていたと伝えられています。
日本では奈良時代からカゼの特効薬として
ショウガ湯が飲まれていたという記録も残っています。
金時ショウガに含まれる成分のジンゲロールやガラノラクトンは、
他のショウガに比べ約4倍も含まれています。
胃酸によって荒れた胃の粘膜を保護して、
胃酸や胃潰瘍を予防・改善する効果があります。
また、金時ショウガは冷え性やセキ、喉の痛み、リウマチ、関節炎、
発熱、悪寒、頭痛など多くの症状を鎮める作用も古くから知られています。
使い方
ヨーグルトに加えたり、黒砂糖やハチミツを加えた
「ショウガ湯ドリンク」がおすすめです。
紅茶に金時ショウガを加えた「ショウガ紅茶」は人気の高い飲み物です。
※簡単、おいしい、豆乳ホットチャイの作り方
鍋にお湯を沸かして、紅茶の葉を入れた後、
金時ショウガ粉末をスプーンで軽く一杯。
(お好みでシナモン・コリアンダー・クミンなどを入れても良い。)
豆乳を水と同量入れてひと煮立ち、熱々のホットチャイのできあがり。
豆乳の甘味と金時ショウガの辛味が絶妙なおいしさで、
体の芯から温まり辛い冷え性ともバイバ~イ!
健康工房 紀の郷
http://www.health-navi.net/
Posted by 健康工房 紀の郷 at
10:47
2008年10月24日
ルテインってどんな成分?
ルテインとブルーベリーは、お互いに目に良い成分として利用されています。
ブルーベリーには、ごぞんじの「アントシアニン」という目に良い成分が含まれています。
ブルーベリーは果実ですが、ルテインは人の瞳(黄斑部)に存在する成分です。
一般的には、ブルーベリーとルテインの組み合わせで使用されています。
ブルーベリーはわかるけど、ルテインってどんな成分?
「ルテイン」は、「カロチノイド」の一種で、野菜や果物に多く含まれ、
人間にとって非常に重要な成分です。
「ルテイン」と「ゼアキサンチン」のカロチノイドは、
人の瞳に存在し、特に”黄斑部”に多く蓄積されていることがわかっています。
しかし、ルテインは加齢や活性酸素などで減少すると、様々なトラブルが発生します。
ルテインは体内で作ることができないので、
食品から積極的に摂取する必要があります。
健康工房 紀の郷
http://www.health-navi.net/
ブルーベリーには、ごぞんじの「アントシアニン」という目に良い成分が含まれています。
ブルーベリーは果実ですが、ルテインは人の瞳(黄斑部)に存在する成分です。
一般的には、ブルーベリーとルテインの組み合わせで使用されています。
ブルーベリーはわかるけど、ルテインってどんな成分?
「ルテイン」は、「カロチノイド」の一種で、野菜や果物に多く含まれ、
人間にとって非常に重要な成分です。
「ルテイン」と「ゼアキサンチン」のカロチノイドは、
人の瞳に存在し、特に”黄斑部”に多く蓄積されていることがわかっています。
しかし、ルテインは加齢や活性酸素などで減少すると、様々なトラブルが発生します。
ルテインは体内で作ることができないので、
食品から積極的に摂取する必要があります。
健康工房 紀の郷
http://www.health-navi.net/
Posted by 健康工房 紀の郷 at
10:19
2008年10月23日
パソコンとブルーベリー
パソコンを利用する方は非常に多くなってきましたね。
毎日の生活に欠かせないものといっても過言ではないでしょう。
実は、私も毎日パソコンをいじりまわしています。
確かに眼の疲れがひどいですね。
皆さんも目が疲れていませんか。
今、子供達もそうですね。
ゲームをやらない子供はいないというぐらい、ゲームに夢中になっていませんか。
実は、我家でも長男が視力が落ちたといって問題になっています。
当分ゲームは取り上げです。
そのような方に強力な味方が現れました。
それがブルーベリーです。
ブルーベリーに含まれるアントシアニンという成分が
目に良い成分だということはご存知ですよね。
今、このブルーベリーを使ったサプリメントがたくさん販売されています。
目が疲れ気味だという方は、このサプリメントをお手元においておくと
ちょっとしたときに手軽に利用することができますね。
ご家族で目の健康維持のために利用されると良いのではないでしょうか。
健康工房 紀の郷
http://www.health-navi.net/
http://www.health-navi.net/ichiran/sizensyokuhin/%20brubery-rutein.html
毎日の生活に欠かせないものといっても過言ではないでしょう。
実は、私も毎日パソコンをいじりまわしています。
確かに眼の疲れがひどいですね。
皆さんも目が疲れていませんか。
今、子供達もそうですね。
ゲームをやらない子供はいないというぐらい、ゲームに夢中になっていませんか。
実は、我家でも長男が視力が落ちたといって問題になっています。
当分ゲームは取り上げです。
そのような方に強力な味方が現れました。
それがブルーベリーです。
ブルーベリーに含まれるアントシアニンという成分が
目に良い成分だということはご存知ですよね。
今、このブルーベリーを使ったサプリメントがたくさん販売されています。
目が疲れ気味だという方は、このサプリメントをお手元においておくと
ちょっとしたときに手軽に利用することができますね。
ご家族で目の健康維持のために利用されると良いのではないでしょうか。
健康工房 紀の郷
http://www.health-navi.net/
http://www.health-navi.net/ichiran/sizensyokuhin/%20brubery-rutein.html
Posted by 健康工房 紀の郷 at
09:51
2008年10月22日
ブルーベリーの成分:アントシアニン

ブルーベリーは、ヨーロッパでは果実を生で食べたり、ジャムやゼリーを作るのに利用しています。
ブルーベリーの成熟した果実は、皆さんご存知のアントシアニンと呼ばれる栄養素で濃い紫色になります。
この成分、アントシアニンが目の健康に大変良いとして今、注目されています。
現代の様々な眼精疲労や眼の疲労には特に有効です。
網膜の機能性低下や白内障を防ぎ、糖尿病が原因の眼の病気予防などに役立ちます。
また、アントシアニンは強力な抗酸化作用もあります。
その他にも、アントシアニンにはコラーゲンを強化する作用や、傷の回復を早める、
筋肉をリラックスさせる、血液をサラサラにして血管の老化や循環障害を改善するなど様々な作用があります。
ブルーベリーは、1976年イタリアで初めて医薬品として製造が承認されたそうです。
その後、ヨーロッパやニュージーランド、韓国など多くの国で医薬品として利用されています。
一度試してみたい方:
http://www.health-navi.net/ichiran/sizensyokuhin/%20brubery-rutein.html
本格的に愛用したい方
http://www.health-navi.net/ichiran/sizensyokuhin/eye-supple.html
健康工房 紀の郷
http://www.health-navi.net/
Posted by 健康工房 紀の郷 at
10:00
2008年10月21日
ブルーベリー(ビルベリー)
 ビルベリーの花
ビルベリーの花ビルベリーは、北欧の森林に生育する野生の多年草落葉低木で、ヨーロピアンクランベリーの近縁種です。
ビルベリーは”目に効く”として、欧州では医薬品として扱われているハーブです。
その有効成分は”アントシアニン”ですが、ブルーベリーと比べて、その質も量も格段に違います。
ビルベリーは、ブルーベリーよりもアントシアニンを豊富に含む健康食品です。
このことによって、健康意識の高い方から注目を集めています。
日本でもビルベリーを使った健康食品がたくさん売られています。
このビルベリーは苗でも売られています。
ビルベリーの花はとても小さくて、ピンクの花を咲かせます。
夏になると紫色の果実をつけます。
鑑賞用としても、食用としても多くの方に愛されているのがビルベリーです。
このビルベリーはサプリメントとして、目を酷使したり、アンチエイジングに気を使われる方には大変おすすめです。
ご家庭では、デザートやジャムとして食卓に出される方もいます。
天然のハーブですので、お子様からご年配の方まで安心してお楽しみいただけます。
苗から育てて観賞用に、またデザートやジャムとしておいしく召し上がったり、
健康、特に目の健康が気になる方はサプリメントをご愛用するすることをおすすめします。
お試しサプリメント
http://www.health-navi.net/ichiran/sizensyokuhin/%20brubery-rutein.html
本格的にご愛用される方
http://www.health-navi.net/ichiran/sizensyokuhin/eye-supple.html
健康工房 紀の郷
http://www.health-navi.net/
Posted by 健康工房 紀の郷 at
10:33
2008年07月31日
漬物・・・乳酸菌とGABA(ギャバ)のダブル効果
もともとビタミンや食物繊維が豊富な野菜ですが、
漬物になるとさらに健康効果がまします。
漬物は、主に乳酸菌の働きで発酵が進みます。
発酵すると野菜のアクが取れて風味が増し、
かさも減るのでたくさん食べれるようになります。
そして、ビタミンやミネラルなどの栄養素も増えます。
ぬか床や野菜といった、植物をエサに殖える乳酸菌は、
過酷な条件下で生きています。
植物の場合は、細胞壁を打ち破って栄養分をとらなければならないからです。
さらに、注目されている漬物の栄養成分が、GABA(ギャバ)です。
GABAは、血圧降下、脳の血流改善、抗ストレス効果などを持っています。
漬物の乳酸菌は、アミノ酸からGABAを作り出す力が強いのです。
発酵が進むほど、GABAの量も多くなります。
☆ まとめ
漬物(キムチや梅干も含む)パワー
1、腸内環境を整える
2、免疫力を上げる
3、高血圧を改善、リラックス効果も
●ビタミン、ミネラルが増える
ダイコンのぬか漬けで見ると、生と比べて、
ビタミンB1が16.5倍、Cと食物繊維が1.3倍、マグネシウムが4倍になる。
●GABAが増える
乳酸菌の働きで、タンパク質がアミノ酸、さらにGABAへと変化する。
アミやイカの塩辛といった動物性タンパク質も使うキムチは
GABAの量が特に多い。
●野菜をたくさん食べられるし食べやすくなる
余分な水分が抜けてカサが減る。
アクや臭みが消え風味も増す。
サラダよりもたくさんの野菜を摂取できる。
健康工房 紀の郷
http://www.health-navi.net/
Posted by 健康工房 紀の郷 at
09:56
2008年07月25日
最強の発酵食 「納豆」
血液サラサラ効果、ピロリ菌も退治する最強の発酵食
今わかっている2つの効能
1つ目は、納豆菌が作り出す酵素、ナットウキナーゼが血液をサラサラにする効果。
同じ作用を持つ医薬品より数十倍も長く、約半日効果が持続する。
脳梗塞は夜中に起こりやすいので、血栓予防のためには夕食で食べる方が良い。
2つ目は、納豆菌が胃ガンや十二指腸潰瘍の原因といわれる、ピロリ菌を減らす効果。
納豆菌は胃酸で死ににくいので、抗菌効果を発揮する。
1日に50gのパック1個を食べればよい。
また食品の中で唯一ビタミンK2を含んでいるのが納豆。
これも納豆菌が作り出すもので、骨を強くして骨粗しょう症を予防する。
納豆は腸内に善玉菌を増やし整腸効果が得られる。
1日50gの納豆を1~2週間食べ続けると、善玉菌が増加し、
悪玉菌が減少して、腸内の腐敗物質も減少します。
効果を得るための1日量・・・・・1パック(50g)
主な有効成分と働き
納豆菌・・・胃のピロリ菌、腸の悪玉菌を減少。
ナットウキナーゼ・・・血液サラサラ。
大豆タンパク質・・・コレステロール低下、心臓病予防。
ビタミンK2・・・骨を丈夫に。
食べ方のコツ
ナットウキナーぜは、70℃以上で壊れるため加熱しないほうがよい。
夜食べると脳梗塞予防に良い。
効果の高い商品選び
粘りが強い糸を引く納豆は発酵状態が良く、納豆菌が多くナットウキナーゼの活性も高い。
健康工房 紀の郷
http://www.health-navi.net/
今わかっている2つの効能
1つ目は、納豆菌が作り出す酵素、ナットウキナーゼが血液をサラサラにする効果。
同じ作用を持つ医薬品より数十倍も長く、約半日効果が持続する。
脳梗塞は夜中に起こりやすいので、血栓予防のためには夕食で食べる方が良い。
2つ目は、納豆菌が胃ガンや十二指腸潰瘍の原因といわれる、ピロリ菌を減らす効果。
納豆菌は胃酸で死ににくいので、抗菌効果を発揮する。
1日に50gのパック1個を食べればよい。
また食品の中で唯一ビタミンK2を含んでいるのが納豆。
これも納豆菌が作り出すもので、骨を強くして骨粗しょう症を予防する。
納豆は腸内に善玉菌を増やし整腸効果が得られる。
1日50gの納豆を1~2週間食べ続けると、善玉菌が増加し、
悪玉菌が減少して、腸内の腐敗物質も減少します。
効果を得るための1日量・・・・・1パック(50g)
主な有効成分と働き
納豆菌・・・胃のピロリ菌、腸の悪玉菌を減少。
ナットウキナーゼ・・・血液サラサラ。
大豆タンパク質・・・コレステロール低下、心臓病予防。
ビタミンK2・・・骨を丈夫に。
食べ方のコツ
ナットウキナーぜは、70℃以上で壊れるため加熱しないほうがよい。
夜食べると脳梗塞予防に良い。
効果の高い商品選び
粘りが強い糸を引く納豆は発酵状態が良く、納豆菌が多くナットウキナーゼの活性も高い。
健康工房 紀の郷
http://www.health-navi.net/
Posted by 健康工房 紀の郷 at
17:02
2008年07月22日
最強の食べる薬~発酵食
健康の要、腸を守ろう!
善玉菌がたくさんいて、腸を元気にする発酵食は、
昔からある一種の家庭の常備薬といつても過言ではありません。
腸は私達の健康維持にとって、最も大切な臓器です。
ガンや病原菌から体を守る免疫力の8割は腸が担っているといわれています。
ストレスを抑え、神経系を活性化させるセロトニンを一番作っているのも腸です。
セロトニンは腸の蠕動運動を促す作用を持っています。
このような腸の活動を活発にするのがコッカス菌をはじめとする腸内善玉菌です。
この善玉菌を増やす菌を大量に含むのが発酵食です。
腸内で善玉菌よりも悪玉菌の力が強くなると様々な健康障害が出てきます。
悪玉菌は腸内腐敗をおこし腸内毒素を生み出しますが、
これが血液に乗って全身をめぐり、
肌荒れや肩こり、倦怠感、口臭などの体の不調を引き起こします。
腸内乳酸菌は、高脂肪型の食生活をしていたり、ストレスにさらされることで減ってしまいます。
また、環境の悪化や高齢化によっても減ってしまうのです。
ですから、悪玉菌が増える要因に囲まれている私達は、
積極的に発酵食を食べることが大切ですね。
善玉菌の多さ、効果の高さ、毎日食べ続けることができる手軽さなどから、
発酵食のベスト3を考えてみました。
それは、「納豆」、「漬物」、「ヨーグルト」だと思います。
どれもいつでも手に入り簡単に手に入れることのできるものばかりですね。
そして、食べ始めると早ければ3日~1週間くらいで
快便や疲労感が軽くなるなどの効果が出てくるのではないでしょうか。
もちろん人によって差は出てきます。
それぞれの腸内の状態が異なるからです。
欠点は、食べるのをやめると効果は数日で消えるということです。
とにかく毎日食べ続けることが大切です。
次回は、3大発酵食のうち納豆について述べましょう。
健康工房 紀の郷
http://www.health-navi.net/
善玉菌がたくさんいて、腸を元気にする発酵食は、
昔からある一種の家庭の常備薬といつても過言ではありません。
腸は私達の健康維持にとって、最も大切な臓器です。
ガンや病原菌から体を守る免疫力の8割は腸が担っているといわれています。
ストレスを抑え、神経系を活性化させるセロトニンを一番作っているのも腸です。
セロトニンは腸の蠕動運動を促す作用を持っています。
このような腸の活動を活発にするのがコッカス菌をはじめとする腸内善玉菌です。
この善玉菌を増やす菌を大量に含むのが発酵食です。
腸内で善玉菌よりも悪玉菌の力が強くなると様々な健康障害が出てきます。
悪玉菌は腸内腐敗をおこし腸内毒素を生み出しますが、
これが血液に乗って全身をめぐり、
肌荒れや肩こり、倦怠感、口臭などの体の不調を引き起こします。
腸内乳酸菌は、高脂肪型の食生活をしていたり、ストレスにさらされることで減ってしまいます。
また、環境の悪化や高齢化によっても減ってしまうのです。
ですから、悪玉菌が増える要因に囲まれている私達は、
積極的に発酵食を食べることが大切ですね。
善玉菌の多さ、効果の高さ、毎日食べ続けることができる手軽さなどから、
発酵食のベスト3を考えてみました。
それは、「納豆」、「漬物」、「ヨーグルト」だと思います。
どれもいつでも手に入り簡単に手に入れることのできるものばかりですね。
そして、食べ始めると早ければ3日~1週間くらいで
快便や疲労感が軽くなるなどの効果が出てくるのではないでしょうか。
もちろん人によって差は出てきます。
それぞれの腸内の状態が異なるからです。
欠点は、食べるのをやめると効果は数日で消えるということです。
とにかく毎日食べ続けることが大切です。
次回は、3大発酵食のうち納豆について述べましょう。
健康工房 紀の郷
http://www.health-navi.net/
Posted by 健康工房 紀の郷 at
16:43
2008年07月08日
血液サラサラ、免疫力を高める伝統食
日本の伝統食には、血液をサラサラにする効果もあります。
血液がドロドロ、ベタベタな状態になると、
動脈硬化が進んだり、血液の流れが悪くなって、
抹消血管の先で酸素や栄養が不足します。
こうした事態を防ぐには、
糖分や動物性脂肪を控え、
日本の伝統食を摂るようにするとよいでしょう。
また、私達の体内では老化を進行させる活性酸素が細胞を傷つけていますが、
こうした内側の敵から身を守る決め手が免疫力です。
日本の伝統食の中でも植物性の食品には、
免疫力を高める抗酸化物質が多く含まれています。
ただし、特定の食品や単一の成分だけでは、
高い効果を期待することはできません。
数種類ずつ、毎日の食卓に取り入れることをおすすめします。
血液のサラサラを助ける食品
酢、黒酢、梅干、納豆、豆腐、ソバ、海藻類、青魚等
免疫力を高める食品
ヒジキ、ワカメ、昆布、玄米、全粒小麦、大麦、大豆、インゲン豆等
血液サラサラを助ける健康食品
秘伝 梅肉黒酢 http://www.health-navi.net/ichiran/sizensyokuhin/bainikukurozu.htm
抗酸化作用のあるお茶
ニワ・ルイボスティー http://www.health-navi.net/ichiran/niwa-sod/ruibosu.htm
健康工房 紀の郷
http://www.health-navi.net/
Posted by 健康工房 紀の郷 at
11:02
2008年07月05日
日本の伝統食でパワーアップ!!
日本の伝統食を見直し、元気パワーを高める食事をしましょう
今、皆さんはどんな食事をしていますか?
日本の伝統食と言えば、米、麦、雑穀、いもが主食。
タンパク質は、豆や豆腐。
外国では日本の伝統食が見直され、日本食ブームと言われています。
素朴な日本の伝統食。
元気パワーの源として見直されています。
有用な成分がたっぷりの味噌や醤油、納豆、ゴマ、漬物と言った発酵食品。
タンパク質だけでなく、カルシウムや食物繊維が豊富な大豆。
肝機能を正しく正常に保つメリオニン、
血中コレステロールを抑制するリノール酸、オレイン酸などが含まれているゴマ。
日本には世界に誇れる豊かな伝統食があります。
ぜひ日々の食生活に日本の伝統食を取り入れてください。
今注目の伝統食
〇味噌
発酵によって、大豆の成分が吸収されやすくなっており、肝臓の強化などに効果が期待できる。
〇漬物
野菜本来のビタミンを壊すことなく、さらに発酵によって新たなビタミンを生成。
ぬかずけには吸収されやすい形でビタミンがある他、
カリウム、亜鉛、鉄、マグネシウムなどミネラルも豊富。
おなかの健康に良い生きた乳酸菌も含まれている。
〇大豆
良質なタンパク質をはじめ、カルシウムや食物繊維もたっぷり。
抗酸化作用のあるビタミンEやイソフラボン、
免疫系を活性化させるレシチンなども含まれる。
〇ゴマ
良質のタンパク質の他、カルシウムやビタミンB1、B2、鉄分などが豊富。
油っぽい料理やアルコールをよくとる人の健康維持に有用なセサミンも含まれている。
健康工房 紀の郷
http://www.health-navi.net/
今、皆さんはどんな食事をしていますか?
日本の伝統食と言えば、米、麦、雑穀、いもが主食。
タンパク質は、豆や豆腐。
外国では日本の伝統食が見直され、日本食ブームと言われています。
素朴な日本の伝統食。
元気パワーの源として見直されています。
有用な成分がたっぷりの味噌や醤油、納豆、ゴマ、漬物と言った発酵食品。
タンパク質だけでなく、カルシウムや食物繊維が豊富な大豆。
肝機能を正しく正常に保つメリオニン、
血中コレステロールを抑制するリノール酸、オレイン酸などが含まれているゴマ。
日本には世界に誇れる豊かな伝統食があります。
ぜひ日々の食生活に日本の伝統食を取り入れてください。
今注目の伝統食
〇味噌
発酵によって、大豆の成分が吸収されやすくなっており、肝臓の強化などに効果が期待できる。
〇漬物
野菜本来のビタミンを壊すことなく、さらに発酵によって新たなビタミンを生成。
ぬかずけには吸収されやすい形でビタミンがある他、
カリウム、亜鉛、鉄、マグネシウムなどミネラルも豊富。
おなかの健康に良い生きた乳酸菌も含まれている。
〇大豆
良質なタンパク質をはじめ、カルシウムや食物繊維もたっぷり。
抗酸化作用のあるビタミンEやイソフラボン、
免疫系を活性化させるレシチンなども含まれる。
〇ゴマ
良質のタンパク質の他、カルシウムやビタミンB1、B2、鉄分などが豊富。
油っぽい料理やアルコールをよくとる人の健康維持に有用なセサミンも含まれている。
健康工房 紀の郷
http://www.health-navi.net/
Posted by 健康工房 紀の郷 at
09:46
2008年07月01日
夏のスタミナ野菜~オクラ
 オクラ、好きですか?
オクラ、好きですか?子供達は大嫌いですよね。
オクラは、別名「青ナットウ」とも呼ばれていて、
ナットウと同じようにネバネバして気持ち悪いですよね。
でも、そのネバネバ大変からだにいいんですよ。
オクラの旬はまさに今、7月から9月。
夏場の露地物は栄養価も高く、
ミネラル、カロチン、ビタミンB、C、Eが豊富に含まれたスタミナ野菜。
まさに夏にぴったり!!
オクラの粘っこさの素、ペクチンは食物繊維で、
腸の働きを良くするばかりでなく、
成人病の予防にも注目されているんですよ。
ペクチンは、水溶性の食物繊維で、
整腸作用が大きく、便秘にも下痢にも効果的。
コレステロールの低下作用も大きい。
オクラの糸をひく要素となっているもう一つの成分がムチン。
ムチンは糖を含む複合タンパク質で、
この中にタンパク質分解酵素が存在するので、
他のタンパク質の消化を助けるんですよ。
ですから、お浸しで食べるときは、
さっと茹でるだけにして、いやだろうけどネバネバは残してね。
ほかにも、カルシウムやβーカロチン、ビタミンC、B1、B2も含んでいます。
嫌いだろうけど、無理をしてぜひ食べてね。
夏のスタミナ野菜の王様だもんね。
どうしても食べるのいやだと駄々をこねる人には、
健康工房 紀の郷が特別オススメの「コッカス プレンティー100」を
すすめちゃうぞ。
http://www.health-navi.net/ichiran/kokkasu-kanren/plenty-100.htm
7月10日~7月31日は、「夏の大感謝セール」なので、
通常10,500円(税込)をこの期間中は8,000円(税込・送料無料)で販売するよ。
その他にも良い物たくさん。
ぜひ一度、健康工房 紀の郷へお越し下さい。
健康工房 紀の郷
http://www.health-navi.net/
Posted by 健康工房 紀の郷 at
10:56
2008年06月26日
生命のコントローラー(8)~ビタミン・ミネラル(微量栄養素)
ビタミン・ミネラルの協力者
ビタミン・ミネラルの働きを補助する栄養素
脂溶性ビタミンのビタミンA、D、Eなどは、
食物中の油に溶けると吸収しやすくなります。
したがって、油の少ない食事では脂溶性ビタミンの吸収が悪くなります。
ビタミンやミネラルが腸の粘膜を通過するときや運び出すときに、
タンパク質の協力が必要になってきます。
また、タンパク質は、ビタミンやミネラルと結合して、
血液の中を移動していきます。
つまり、タンパク質が少ない食物では、
ビタミンやミネラルの吸収に影響がでてきます。
ミネラルの多くは、
酵素(化学反応を促進させるためのタンパク質)の構成成分となって、
機能を果たしています。
したがって、酵素となるタンパク質がしっかりと合成されなければ、
ミネラルの機能が半減してしまいます。
ビタミンやミネラルが効率よく働くには、
補助してあげる他の栄養素が必要です。
ビタミン・ミネラルだけでは効果が半減・・・事例
飢餓地域の人たちは、ビタミンAの欠乏により、
失明してしまう問題があります。
この人たちにビタミンAを投与するだけでは、
失明の予防にならないことがわかっています。
ビタミンAの投与と同時に、
その他の栄養状態を改善しなければ、
失明の予防にならないのです。
つまり、ビタミンやミネラルが効率よく働くには、
補助してあげる他の栄養素が必要です。
最後に、バランスの良い食事が大切です
ビタミン・ミネラルは、
私達人間のからだを調節するという、とても重要な働きをしています。
その重要性から、
論文や文献によっては三大栄養素の炭水化物、脂質、タンパク質と
ビタミン・ミネラルをあわせて「五大栄養素」と位置づけているものもあるほどです。
さらに、最近の研究から「薬理効果」を見出され、
ビタミン・ミネラルの果たす役割は、
まさに私達人間の「生命のコントローラー」なのです。
しかし、健康を維持するためには、
特定のビタミン・ミネラルだけを摂取すればよいものではありません。
私達人間のからだはとても複雑に出来ていて、
ビタミン・ミネラルは相互に関係しながら、
他の栄養素に助けられて、はじめて効率よく効果を発揮します。
したがって、
私達の健康を維持するためには、
いろいろな食物をバランスよく食べることが重要です。
健康工房 紀の郷
http://www.health-navi.net/
Posted by 健康工房 紀の郷 at
14:07
2008年06月23日
生命のコントローラー(7)~ビタミン・ミネラル(微量栄養素)
ビタミン・ミネラルによる予防と回復
薬の機能
ビタミンやミネラルは栄養素としての役割があります。
ところが、最近の研究では、
栄養素のほかに新しい機能を期待するようになってきました。
それは、病気に対して薬として働いたり、
病気への予防の効果が出る「薬理効果」という機能です。
例えば、
骨粗鬆症の予防は、ビタミン・ミネラルが大きく関与していることは周知のことです。
さらに、食事などが深くかかわっているガン、心疾患、脳疾患などの成人病の予防に、
効果があることがわかってきました。
このように「薬理効果」が見出されたことによって、
ビタミン・ミネラルは広く関心がもたれています。
免疫力を上げる
人間には、自然に治癒する能力があり、
自律神経系、ホルモン系、免疫系の三つのバランスが大切とされています。
その中の免疫とは、私達人間のからだが、
侵入してきた病原菌などや変異したガン細胞などを除去することです。
この免疫力を向上させるものとして、
ビタミンA、C、Eがあります。
※病気の予防と回復のための栄養素
ガン
ビタミンA、B群、C、E、セレン
心臓病
ビタミンB群、C、E、カリウム、カルシウム
骨粗鬆症
カルシウム、マグネシウム、ビタミンC、D
糖尿病
ビタミンB群、C、E、ナイアシン、クロム、マンガン
更年期障害
ビタミンB群、C、E、鉄、セレン
脳卒中
ビタミンB群、C、E、亜鉛、マグネシウム、マンガン
アレルギー・ぜん息
ビタミンA、B群、C、E、マンガン
リュウマチ
ビタミンB群、C、E、カリウム、カルシウム
胃潰瘍・十二指腸潰瘍
ビタミンA、B群、E
貧血
ビタミンB群、C、E、葉酸、鉄、銅、マンガン、マグネシウム
神経痛
ビタミンB群、C、E、ナイアシン、パントテン酸、マグネシウム
健康工房 紀の郷
http://www.health-navi.net/
Posted by 健康工房 紀の郷 at
10:31